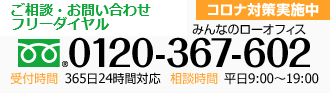後遺障害についてのよくある質問
質問をクリックすると詳細が表示されます
-
後遺障害とは、何ですか?「後遺症」と「後遺障害」の違いを教えてください。
「後遺症」とは、病気や怪我の治療を続けたものの、完治せずに残った症状のことをいいます。
一方で、「後遺障害」とは、後遺症のうち、労働能力の喪失を伴い、自動車損害賠償保障法に定められた1級から14級までの後遺障害等級に該当するものをいいます。「後遺障害(等級)」の認定を受けることで、「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」を受け取ることができます。
「後遺障害慰謝料」とは、交通事故被害者が受けた精神的な苦痛のうち、後遺障害が残った場合に支払われるものです。「後遺障害逸失利益」とは、事故に遭わなければ得られるはずであった、将来の給料や収入のもののうち、後遺障害が残ったことが原因となるものです。
逆に言えば、後遺障害等級の認定を受けられない場合、症状固定後は「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」を受け取ることができません。 -
私は、交通事故でケガをして、6か月以上治療をしましたが、まだ痛みなどの症状を残して症状固定で治療が終了しました。
交通事故で治りきらない症状が残ったので、後遺障害が認定されると考えて間違いないですか?症状固定時に、症状が完治しなかった場合、その残った症状は「後遺症」に当たりますが、必ずしも「後遺障害」が認定されるとは限らないため注意が必要です。
「後遺症」とは、病気や怪我の治療を続けたものの、完治せずに残った症状のことをいいます。一方で、「後遺障害」とは、後遺症のうち、労働能力の喪失を伴い、自動車損害賠償保障法に定められた1級から14級までの後遺障害等級に該当するものをいいます。
後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益が認められるのは、「後遺障害」認定を受けた場合に限られますが、この認定を受けるには一定の手続きを経る必要があります。その手続きを簡単に説明すると、①後遺障害診断書などの書類を医師に作成してもらい、②後遺障害等級の申請を行います。そして、③提出した資料を基に該当・非該当や、等級の判断がされます。④この審査結果に納得いかない場合には、不服申立てとしての手続きも準備されています。⑤最後に、後遺障害等級を踏まえて、加害者(保険会社)と賠償交渉を行います。
以上のような手続きを経て、後遺障害認定を受けることで初めて、後遺障害慰謝料等を請求することができます。
-
自賠責保険の後遺障害には、どのような種類の後遺障害がありますか?
自賠責保険は、「後遺障害等級」として、要介護1級・要介護2級と、要介護でない1級から14級のものを定めています。
1級が一番重い後遺症で、14級が後遺障害が認定される中では一番軽い後遺症ということになります。等級に応じて、自賠責保険の「(最大の)保険金」や、後遺障害逸失利益の算定に用いる「労働能力喪失率」などが変わります。
要介護ではない後遺障害1級が認められる具体例としては、「両目を失明した場合」(1号)や、「両上肢を肘関節以上で失った場合」(3号)などが挙げられます。この場合には、自賠責の保険金は最大3000万円となり、労働能力喪失率も100%とされます。
一方で、後遺障害14級が認められる典型例としては、交通事故の衝撃によるむち打ちの症状で首や膝などに神経痛が残った場合などが考えられます。この場合に、「局部に神経症状を残すもの」(9号)に該当すれば、自賠責の保険金は最大75万円、労働能力喪失率は5%となります。
もっとも、14級9号に該当するか否かは、加害者側保険会社との間で争いとなることが多いです。非該当となれば、後遺傷害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できなくなるため、14級9号に該当する症状が残っていることを立証する必要があります。 -
自賠責保険で後遺障害が認定される割合を教えてください。
「交通事故被害者が後遺障害の申請を行った件数のうち、後遺障害が認められた件数の割合」については、正確な数値を把握することはできません。もっとも、それに類似したものとして、「自賠責保険が賠償金として支払った件数のち、後遺障害が認定された件数の割合」については、自賠責保険の後遺障害等級の認定を行う「損害保険料算出機構」が毎年発表する「自動車保険の概況」から算出することができます。
自動車保険の概況2023年度版を参照すると、自賠責保険が2022年度中に賠償金を支払った件数は、842,035件となっています。そのうち、後遺障害等級が認められたのは、33,933件となっており、割合としては、約4%となっています。この数値には、交通事故によりお亡くなりになった方や、後遺障害申請をしなかった方も母数に含まれておりますので、単純に後遺障害が認定される割合とはいえません。
しかし、傷害と認定された件数が805,415件(約95.6%)となっていることからすると、後遺障害の認定には高いハードルが設けられているといえるでしょう。その認定には、後遺症の状況が後遺障害等級1級ないし14級に該当することを立証する必要がありますが、その立証には、これまでの裁判例や専門的な知識も必要となりますので、弁護士に相談して、後遺障害の認定を狙うことも一つの手段です。
-
後遺障害診断書の作成費用は、保険会社に請求することができますか?
「後遺障害診断書」は医師が作成する診断書であり、これがなければ、後遺障害の認定を受けることができないほど重要なものと言えます。
その作成費用については、基本的には、後遺障害が認定された場合には、加害者の保険会社に請求することができ、後遺障害が認定されなかった場合には保険会社には請求することができない(被害者の自己負担)と考えられます。具体的には、以下のようなケースが考えられます。
①保険会社が一括対応をしている場合 相手方保険会社が一括対応(保険会社が治療費を病院に直接支払うサービス)を行っている場合、後遺障害診断書の作成費用の支払も一括対応の中に含まれています。そのため、一括対応の場合には、基本的には保険会社が作成費用を負担してくれるということになります。
②保険か一社が一括対応をしていない場合 この場合、まずは自費で後遺障害診断書の作成費用を負担することになります。そして、後遺障害が認定された場合には後から保険会社にその作成費用の支払を請求することができます。一方で、後遺障害が認定されない場合、保険会社との交渉次第によっては支払いに応じることもありえますが、基本的には保険会社は支払に応じないと考えられます。
-
後遺障害が認定されると、何を請求することができますか?
後遺障害が認定された場合、被害者は、保険会社に対して、「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」を請求することができます。
「後遺障害慰謝料」とは、交通事故被害者が受けた精神的な苦痛のうち、後遺障害が残った場合に支払われるものです。「後遺障害逸失利益」とは、事故に遭わなければ得られるはずであった、将来の給料や収入のもののうち、後遺障害が残ったことが原因となるものです。
逆に言えば、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益は、後遺障害認定を受けない限り請求できないため、後遺障害認定を受けることがとても大切です。 -
後遺障害慰謝料の算定方法を教えてください。
後遺障害認定を受けた場合、被害者は「後遺障害慰謝料」を請求することができます。後遺障害等級が高くなるほど(1級に近いほど)、慰謝料の金額は大きくなるといえます。もっとも、慰謝料額は、等級だけでなく、いかなる基準を採用するかによっても前後しますので、3つの基準を紹介します。
①自賠責保険が定める「自賠責基準」では、必要最小限の補償を果たすために、賠償金額は小さくなる傾向にあります。
②任意保険会社が定める「任意保険基準」では、自賠責基準よりかは若干高い支払基準を望めるものの、後述の弁護士基準(裁判基準)よりは低い支払基準となります。
③これまでの裁判例を基に形成された「弁護士基準(裁判基準)」では、上記の2つの基準よりも高額な慰謝料の支払を認める基準です。慰謝料が高額となるため、この基準に基づいた慰謝料を請求するにあたっては、保険会社との交渉を要します。交渉には、後遺症の状況や後遺障害等級、これまでの裁判例との適合性など、専門的な知識を要しますので、「弁護士基準」の後遺障害慰謝料を請求するにあたっては、弁護士に相談・依頼することが推奨されるといえます。
-
逸失利益の算定方法を教えてください。
「逸失利益」とは、交通事故に遭わなければ、得られたであろう収入が得られなくなった場合において発生する損害のことをいいます。逸失利益は、症状固定(治療をこれ以上継続しても、症状の改善が見込めない状態のこと)の前後によって、その性質が変わります。
症状固定前は、治療等により働けず、得られなかった収入分が「休業損害」となります。休業損害の算定は、「基礎収入(日額)」×「休業日数」で計算します。休業損害は、既に発生した損害の実額を請求することになるので、損害額の算定が比較的容易であるといえます。
症状固定後は、休業損害は請求できませんが、後遺障害が認定された場合には、その代わりに「後遺障害逸失利益」を請求することができます。「後遺障害逸失利益」は、被害者に後遺障害が残り、労働能力が減少したため、将来発生するであろう収入が減少したことから、その賠償を求めるものです。後遺障害逸失利益の算定は、「基礎収入」×「労働能力喪失率」×「(労働能力喪失期間に応じた)中間利息控除係数」で行います。
まず、「基礎収入」は、これまでの収入を踏まえた、1年当たりの収入をいいます。給与所得者であれば事故前年分の源泉徴収票や課税証明書を、事業所得者であれば確定申告書や収支内訳書(又は青色申告決算書)を踏まえて算出します。
次に、「労働能力喪失率」は、後遺障害により労働能力がどれほど低下したかを示す割合です。後遺障害等級に応じてその割合は変わります。たとえば、後遺障害等級1級であれば喪失率100%となるのに対し、14級であれば喪失率5%にとどまります。最後に「(労働能力喪失期間に応じた)中間利息控除係数」についてです。「労働能力喪失期間」は、労働能力の喪失による収入の減少が続く(と考えられる)期間をいいます。後遺障害認定がされた場合、その開始時期(始期)は症状固定時であり、終了時期(終期)は67歳になるまでとされています。ただし、「症状固定時の年齢の平均余命の2分の1」が、上記の「労働能力喪失期間」を上回る場合、「当該平均余命の2分の1の年数」を用いて計算します。例えば、症状固定時に被害者が60歳男性である場合、労働能力喪失期間は、7年(=67-60)となります。
「中間利息控除」とは、後遺障害逸失利益が将来受け取るべき収入をあらかじめ受領することになる関係で、それを現在の価格に引き直すために用いる数値のことをいいます。一般的には、「ライプニッツ係数」が用いられ、表として一覧化されています。例えば、18歳以上の被害者の就労可能年数が①1年であれば、0.9709、②10年であれば、8.5302をかけることになります。なお、「ライプニッツ係数」の他に「ホフマン係数」が用いられることもありますので、場合に応じて必要な係数を確認する必要があります。
-
交通事故の前後で減収がない場合は、逸失利益が認められることはありませんか?
「逸失利益」とは、交通事故により生じた後遺障害によって、将来的に労働能力が低下し、得られたはずの収入の減収分のことをいいます。
交通事故の前後で減収がない場合、事故後も収入に変動がないため、基本的には逸失利益は0ということになります。そうだとすれば、加害者に対して逸失利益を請求することはできません。
しかし、減収がないように思える場合であっても、例外的に逸失利益が認められることは考えられます。具体的には、①本人の努力や②職場の対応により、「(本来減収される状況にあるものの、)減収せずに済んでいる場合」や、③昇進・昇給の機会を喪失した場合、④職業選択の制限を強いられた場合など、「実際には、将来的に収入が減少したといえる場合など」が考えられます。
-
交通事故当時、若くてまだ働いていない人は、どのように逸失利益を算定するのですか?
「逸失利益」とは、交通事故により生じた後遺障害によって、将来的に労働能力が低下し、得られたはずの収入の減収分のことをいいます。
そのため、交通事故被害者がまだ働いていない場合、交通事故の前後で減収がないため、事故後も収入に変動がなく、基本的には逸失利益は0ということになります。
もっとも、「被害者の方が(若く)将来的に働く蓋然性があるといえる場合」には、将来的に得るはずであった収入が減少したといえ、例外的に逸失利益が認められることがあります。年齢や学歴などの要素を踏まえて将来的に働く蓋然性が判断されますが、年齢が若い場合にはこの蓋然性は認められやすいといえるでしょう。「逸失利益」の算定は、「基礎収入」×「労働能力喪失率」×「(労働能力喪失期間に応じた)中間利息控除係数」で行います。このうち、「労働能力喪失率」は後遺障害等級に応じて、「労働能力喪失期間」や「中間利息控除係数」は年齢に応じて、それぞれ判断されますので、その数値はすぐに導き出すことが可能です。
これに対して、「基礎収入」については、事故当時に収入がない場合、その算定は容易ではありません。もっとも、学生など若年の方が働いていない方が被害者の場合、「平均賃金(賃金センサス)」を将来的に得られた収入であるとして、これを基礎収入の一つの目安として算定することが考えられます。これが認められるには、被害者が、将来的に「平均賃金」を得られる蓋然性があることを立証する必要があります。その際には、被害者の年齢や学歴、就労意欲、(過去に働いたことがある場合には)所得の推移などが考慮されます。
-
まだ若くて収入が低い人も、交通事故の前年の収入をもとに逸失利益を算定するのですか?
「逸失利益」とは、交通事故により生じた後遺障害によって、将来的に労働能力が低下し、得られたはずの収入の減収分のことをいいます。
そのため、基本的には、事故前と事故後の収入を比較することになるため、原則として事故前の収入が前提となります。
もっとも、交通事故被害者の方が、事故当時は若くて収入が低いものの、将来的には収入が増えていたと考えられる場合には、その点を考慮して逸失利益を算定します。「逸失利益」は将来的に得られるはずであった収入の減少に着目するものであるからです。「逸失利益」の算定は、「基礎収入」×「労働能力喪失率」×「(労働能力喪失期間に応じた)中間利息控除係数」で行います。若年労働者など収入が少ないものの、将来的には収入が増加する蓋然性がある方については、「基礎収入」の算定では、昇給昇進の可能性や、職業選択の制限の程度などが考慮されます。
-
家事従事者(主婦)にも逸失利益は認められますか?
「逸失利益」とは、交通事故により生じた後遺障害によって、将来的に労働能力が低下し、得られなかったであろう収入の減収分のことをいいます。そして、家事労働についても経済的な評価をすることができますので、逸失利益が認められる場合が十分あります。
「逸失利益」の算定は、「基礎収入」×「労働能力喪失率」×「労働能力喪失期間」×「(就労可能年数に応じた)中間利息控除係数」で行います。このうち、家事労働の基礎収入については、実務上「女性の全年齢の平均賃金」が用いられます。なお、家事労働に逸失利益が認められることについては、男性も同様(いわゆる「主夫」)ですが、この場合でも「女性の全年齢の平均賃金」が基礎収入となります。
-
逸失利益が争われやすい職業はありますか?
「逸失利益」は、将来的に得られたであろう収入がどれほど減少したかということが問題となります。そのため、「将来得られたであろう収入」の算定が難しい場合には、逸失利益の金額について、被害者側と加害者側(保険会社)との間で争われやすいといえます。具体的な職種としては、歩合制が採用されているものや、自営業者・フリーランスなどが考えられます。また、若年労働者や学生の場合、将来的な昇進・昇格に伴う収入の上昇も考えられるため、その金額についても争われやすいといえるでしょう。
-
逸失利益が争われやすい後遺障害はありますか?
「逸失利益」とは、交通事故により生じた後遺障害によって、将来的に労働能力が低下し、得られたはずの収入の減収分のことをいいます。逸失利益が争われやすい後遺障害としては、「当該後遺障害が、労働能力にどのような影響を与えるかが不明確である場合」が考えられます。
具体的には、①外貌醜状や②味覚・嗅覚の後遺障害などが考えられます。いずれの場合も、後遺障害と認められたとしても、一般的な職種において直ちに労働能力が低下するものといえるかが微妙となるケースが多いです。
そのため、加害者側保険会社としては、「労働能力が低下していない」と主張して、逸失利益の存否・額を争うことが考えられます。しかし、被害者の従来の職種によっては、上記のような後遺障害の場合でも、労働能力の低下につながることは十分考えられます。たとえば、俳優やモデルなど外見が重視される仕事をされている方が①外貌醜状の後遺障害が残った場合、その仕事に影響が出ることが十分考えられます。
また、料理人や食品開発などを行う仕事をされている方が②味覚・嗅覚の後遺障害が残った場合なども同様です。
以上のように、一見「後遺障害の内容」と「労働能力の低下」が結びつかないように思える場合でも、被害者の具体的な職務内容などを考慮することで、逸失利益が認められることも十分考えられます。 -
後遺障害の認定は、誰が行うのですか?
後遺障害の認定は、まず、自賠責保険が行いますが、その判断をしているのは「損害保険料算出機構」という機関です。認定までの手続きの流れとしては、以下のようになります。
1 症状固定後、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらい、これ含む必要書類を自賠責保険に提出する(自賠責保険は損害保険料算出機構に等級認定を委託する)。
2 損害保険料算出機構が原則「書面審査」のみを実施し、後遺障害等級の認定を行う。
3 認定結果に納得がいかない場合には、被害者は不服申立てをすることができる。
そして、3の不服申立ての方法としては、①「自賠責保険(≒損害保険料算出機構)に対する再申請」、②「一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構での調停申立て(紛争処理制度)」、③「民事訴訟(裁判)」の選択肢があります。
①は何度も利用することができますが、判断者は引き続き「損害保険料算出機構」となります。再申請で満足のいく後遺障害等級認定を得るには、先の認定に至った原因を分析したうえで、資料を補充し、先の認定が不合理であることを示す主張とこれを裏付ける証拠を準備する必要があるでしょう。
②は1回のみ利用できる不服申立て手段です。「一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構」は、自賠責保険の保険金の支払いについて生じた紛争につき、的確かつ公正な解決を図り、被害者保護を実現するために設立された機構です。①と異なり、第三者的立場にある機構が、適切な後遺障害等級の認定を行うという特徴があります。
③は、「損害保険料算出機構」や「一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構」による「後遺障害等級の認定の判断自体」について争うのではなく、「損害賠償額全体」を争う手段です。そのため、民事訴訟を提起しても、既になされた後遺障害等級の認定が変わるということにはなりません。また、裁判となれば、判決が出るまで時間がかかることに留意する必要があります。
いずれの方法をとる場合であっても、満足のいく後遺障害等級の認定や損害賠償額を獲得するには、主張構成や証拠収集、過去の事案との比較などに高い専門性が要求されます。その点、弁護士に相談・依頼することは、交通事故被害者の方が納得できる結果を得るために、非常に有効な手段であるといえます。ぜひご検討ください。
-
自賠責保険の後遺障害手続には、「事前認定」という手続と「被害者請求」という手続の2種類の手続があると聞きました。
それぞれ、どのような手続なのか教えてください。まず、自賠責保険の後遺障害手続の概要としては、以下のようになります。
1 症状固定後、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらい、これ含む必要書類を自賠責保険に提出する(自賠責保険は損害保険料算出機構に等級認定を委託する)。
2 損害保険料算出機構が原則「書面審査」のみを実施し、後遺障害等級の認定を行う。
3 認定結果に納得がいかない場合には、被害者は不服申立てをすることができる。
このうち、1の必要書類の提出は、「加害者の自賠責保険会社」に対する後遺障害の申請手続の一環としてなされますが、その方法として、①「被害者請求」と②「加害者請求(事前認定)」とがあります。
①「被害者請求」とは、申請者たる被害者が「後遺障害診断書」など必要書類を全て集めたうえで、後遺障害手続の申請を行う方法です。書類を集めることに手間はかかりますが、その書類の内容を確認し、医師に問い合わせたり、資料の補充ができたりすることから、満足のいく後遺障害等級の認定を受けやすくなるメリットがあります。
②「加害者請求(事前認定)」とは、申請者たる被害者は「後遺障害診断書」を加害者側保険会社に提出するのみで、加害者側保険会社が残りの書類を用意したうえで、後遺障害手続の申請を行う方法です。①の方法と比較すると、被害者にとって手続の準備の手間を省くことができます。しかし、②の方法では、後遺障害診断書以外の書類について、その内容を確認できないままとなります。そのため、満足のいく後遺障害等級の認定を受けるための対策(資料補充など)をおこなうことができないため、加害者側保険会社が「後遺障害等級非該当」や「事故と後遺障害の因果関係」などで争うことを考えているケースでは、加害者側保険会社の主張が通る可能性も高まるといえるでしょう。
上記のように、①②それぞれの手続のメリット・デメリットを踏まえると、満足のいく後遺障害等級の認定を得るには、多少手間をかけても、認定を得るための証拠をしっかり準備できる①被害者請求の方が無難と考えられます。また、必要書類の収集は、弁護士に依頼することも可能です。弁護士は、過去の後遺障害についての判断を踏まえつつ、医師面談などを行い、必要な主張・証拠を集めることができ、満足のいく後遺障害等級の認定を得やすくなるといえるでしょう。
-
後遺障害の手続をする際、事前認定で手続をするか、被害者請求で手続をするかで、認定のされやすさは違いますか?
いずれの手続も取ることも可能ですが、事実上、「被害者請求」の方が認定されやすい傾向にあります。
その理由は、事前に被害者側で提出書類の内容を確認することができる点にあります。後遺障害等級認定は、損害保険料算出機構が、申請者から提出された必要書類のみを審査すること(書面審査)が原則であるため、満足のいく後遺障害等級認定を得るには、提出書類(後遺障害診断書や、交通事故証明書、レントゲン画像など)の記載内容が特に重要になります。
ここで、「被害者請求」の場合、被害者の方で、必要書類一式を集めて申請を行うことになりますが、その過程で書類の記載内容を確認することができます。そのため、たとえば、医師との疎通が上手くいっておらず、後遺障害診断書に適切な記載がなされていない場合、医師との面談を通じて修正をお願いすることが可能です。また、書類が不足していると考えれば、提出する書類を追加することも可能です。
一方で、「事前認定(加害者請求)」の場合、後遺障害診断書の準備以外は、加害者側の保険会社で行うことになり、被害者は、「申請に必要な書類の準備・確認」に関与することができません。そのため、「被害者請求」の場合のように、後遺障害等級の認定のために被害者側で動くことができず、結果的に満足のいく後遺障害等級の認定を得られにくくなるといえるでしょう。
被害者が「事前認定」の手続を選ぶメリットは、必要書類の準備を行う手間を省くことができる点にあります。しかし、「被害者請求」の手続を選んだ場合でも、弁護士に依頼することでその手間は必要最小限に抑えることが可能ですし、何より満足のいく後遺障害等級の認定を得やすくなるといえるでしょう。
-
自賠責保険において後遺障害等級が認定されました。将来悪化した場合、後遺障害等級が変わることはあるのですか。
将来悪化した際に、再度、悪化した症状が固定した段階で後遺障害診断書を作成し、自賠責保険に請求を行えば、後遺障害等級が変わることはあります。
-
自賠責保険の後遺障害の手続と労災の後遺障害の手続を、両方行うことはできるのでしょうか?
労災保険が適用される場面において、交通事故に遭った方については、自賠責保険の後遺障害の手続と労災の後遺障害の手続を両方行うこと自体は可能です。
ただし、自賠責保険における「逸失利益」と労災保険における「障害(補償)給付」は、補償内容が重複するため、いずれか一方からしか受け取ることができません。両方の補償を受けることができれば、事故によって被害者が(金銭的に)得することになるからです。
-
自賠責保険の後遺障害の手続と労災の後遺障害手続の違いを教えてください。
労災保険が適用される場面で、交通事故に遭った方は、自賠責保険の後遺障害手続若しくは労災の後遺障害手続、又はその両方の手続を選択することが可能ですが、両手続には以下のような違いがあります。
(1)申請先
自賠責保険では「加害者の保険会社」となるのに対し、労災保険では「労働基準監督署」となります。
(2)審査方法
自賠責保険では、申請時に提出された必要書類一式についての「書面審査」が原則となります。一方で、労災保険では、所定の様式の書類を作成の上、障害(補償)給付申請を行った後、被害者は、労働基準監督署において、「嘱託医の診断」を受ける必要があるなど、詳細な審査が行われます。
なお、後遺障害等級については、共通の基準が用いられていますが、審査内容が違うため、審査結果たる認定に違いが生じる可能性はあります。
-
交通事故でむちうちになりました。近いうちに症状固定として後遺障害の手続をすることになりました。後遺障害の手続をするにあたり、主治医に頚のMRIの撮影をお願いしたら、「撮影しても意味ないよ」と言われ、煙たがられました。もう一度、主治医にMRIの撮影を頼むのも気まずいです。MRIの撮影をせずに、後遺障害の手続をすることはできますか?
後遺障害手続をするにあたって、MRIの撮影は必須でないため、MRIの撮影がなくても後遺障害手続を行うことは可能です。
しかし、むち打ちの症状がある場合、以下の「MRIの特徴」から、MRI撮影をしておいた方が望ましいといえるでしょう。レントゲン撮影では基本的に骨しか写らないのに対し、MRIは、骨だけでなく、脊髄や椎間板なども写すことが可能です。
そのため、MRIは、交通事故の後遺障害として多い「むち打ち」の症状を、画像により立証するにあたって重要になります。後遺障害等級14級9号の「局部に神経症状を残すもの」の立証には、必ずしも画像所見は必要ではないものの、画像所見があった方が立証しやすいといえるでしょう。さらに高い等級である12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」の立証には、基本的にMRIによる画像所見が必要となるでしょう。
このように、むち打ちにつき後遺障害等級を得るには、MRIの撮影がとても重要な意義を有しています。
主治医がMRIの撮影に消極的であっても、MRI撮影の重要性を説明したうえで、その撮影をしてもらった方が望ましいです。 -
自賠責保険と労災で、同一の事故にもかかわらず異なる後遺障害が認定されることはありますか?
自賠責保険と労災の間で、異なる後遺障害が認定される可能性はあります。
自賠責保険では、申請時に提出された必要書類一式についての「書面審査」が原則となります。一方で、労災保険では、所定の様式の書類を作成の上、障害(補償)給付申請を行った後、被害者は、労働基準監督署において、「嘱託医の診断」を受ける必要があるなど、詳細な審査が行われます。
そのため、自賠責保険と労災保険の後遺障害手続は、認定基準が共通するものの、審査方法に違いがある結果、異なる後遺障害等級が認定されることがあります。 -
自賠責保険から判断された後遺障害等級に納得がいかず、自賠責保険に対して異議を申し立てました。結果が出るまでにはどれくらいの期間を要するでしょうか。
自賠責保険(損害保険料算出機構)に対する異議申立ては、結果が出るまでに2~6か月ほどかかると考えておくと良いでしょう。
後遺症の内容や医療照会の有無によって変化しますが、最初の審査と比較すると、期間を要する傾向にあるといえるでしょう。 -
前にも後遺障害の等級を獲得しています。今回、別の交通事故に遭ってしまったのですが、改めて後遺障害の申請をすることはできるのでしょうか。
申請自体は可能なのですが、新たな後遺障害が認定されるか否かが問題となります。基本的には次の通り考えられます。
1「同部位に症状が残存した場合」
この場合は、加重障害、つまり、前回認定された後遺障害を上回る障害が残存しなければ等級の認定はなされません。
例えば、右足首の機能障害で12級が認定されており、重ねて右足首を負傷した場合、結果、12級の後遺障害が残存したとしてもそれは前回認定の後遺障害が残存しているだけとなり、新たな等級は認定されませんが、より重度な障害(この例で言いますと8級や10級の機能障害)が残存した場合は加重障害として認定されます。2「別部位に症状が残存した場合」
先の例で言いますと、右足首に12級の機能障害が残存していた方が、今回新たに左足首に12級の機能障害が残存した場合は、通常通り後遺障害等級の認定がなされます。
-
過去に労災で後遺障害の等級が認定されています。自賠責の後遺障害の認定に影響はありますか。
直接の影響はありません。但し、過去に労災で後遺障害として認定された症状等につき、自賠責保険においても「障害」と認定されれば、それは既存障害となります。
-
加重とは何ですか。
既に後遺障害が残存していた人が、さらに交通事故により同部位の障害を重くした場合を指します。
-
後遺障害等級が認定されましたが、等級に応じた自賠責保険金額から、既存障害として認定された等級に対応する金額が減額されて支払われました。争うことはできないでしょうか。
自賠責保険に対する異議申立手続において、既存障害はもっと低い、もしくは無いとの争いは可能です。但し、その既存障害が過去に自賠責保険で認定を受けたものである場合は、自賠責で争うことは困難であり、裁判で争うこととなります。