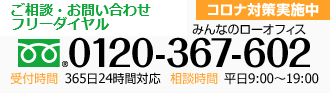事故直後の対応についてのよくある質問
質問をクリックすると詳細が表示されます
-
交通事故に遭った場合、その場で何をすべきでしょうか。
まずは、自己の身や周りの方の安全を確保するようにしましょう。
安全を確保した後、110番で、警察に事故の報告をしてください。道路交通法上、ドライバーには、人身事故・物損事故を問わず、事故報告義務があります。警察に連絡しない場合、交通事故が起きたことを公的に証明する「交通事故証明書」が発行されません。「交通事故証明書」が発行されないと、事故に関する保険金請求をすることも難しくなります。
事故報告以外にも、①事故の相手方の名前や連絡先、車両ナンバー、保険情報などを確認し、メモしておきしょう。これらの情報は、今後、相手方やその保険会社に対して損害の賠償を求めるにあたって必要になります。
また、②事故現場や、被害車両・加害車両の破損状況などを写真・動画に撮って記録することも行いましょう。損害の賠償を求めるにあたり、事故状況を立証する重要な証拠となる可能性があり、それが賠償額に影響しうるからです。事故現場などの撮影については、詳しくは、こちらの回答をご参照ください。
-
交通事故が発生した場合、スマートフォンなどで何か撮影した方が良いでしょうか。
事故現場や被害車両・加害車両の状況を写真に撮って残しておきましょう。
具体的には、両車両の位置関係や、道路に飛散した車両の破片、両車両の破損状況を撮影しましょう。これらを撮影することで、事故状況を正確に記録することができ、事故状況に関する証拠として残すことができます。
また、人身事故であれば、警察が交通事故の状況について現場検証を行った内容を基にして「実況見分調書」が作成されるのに対し、物損事故の場合、「実況見分調書」が作成されません。そのため、物損事故の場合、事故態様の立証のためには、「事故直後に撮影した事故現場の写真・動画」が、事故態様の立証のために特に重要になります。
他にも、自己の相手方の免許証を撮影することが可能であれば、これを撮影しておくこともおすすめします。免許証を撮影しておくことで、後になって相手方と連絡が取れなくなるリスクを避けることができますし、示談や訴訟の準備を迅速に行いやすくなります。
-
交通事故にあいましたが、お互いの車にドライブレコーダーは付いていませんでした。
事故の発生状況を証拠化するためにできることはありますか?ドライブレコーダーがない場合でも、事故の状況を証拠化するためにできることはあります。
道路交通法上、交通事故が発生した場合、人身事故・物損事故問わず、ドライバーには、警察に交通事故が発生したことを報告する義務があります。そして、ドライバーが報告することで、警察による現場検証が行われます。人身事故であれば、警察が交通事故の状況について、現場検証を行った内容を基にして「実況見分調書」が作成されます。
「実況見分調書」自体は、刑事裁判のために作成されますが、民事においても、事故態様を立証する重要な証拠となります。警察に「実況見分調書」を作成してもらうためにも、警察へ事故を報告しましょう。
また、警察へ連絡した後には、事故現場や両当事者の車両の破損状況などを撮影しましょう。特に物損事故の場合、「実況見分調書」が作成されないため、事故態様を立証するための証拠を当事者自ら残しておくことが大切です。
さらに、交通事故の目撃者がいる場合、その連絡先を聞いておきましょう。「目撃者の証言」が事故態様の立証に役立つケースもあるからです。 -
交通事故にあいましたが、相手の車が現場から走り去ってしまいました。
どのようにしたら良いでしょうか。まずは、相手方本人の特徴や、相手方の乗車していた車両の特徴・ナンバーを覚えている場合には、記憶があいまいになる前にすぐにメモしておきましょう。
これらの情報は、走り去ってしまった加害者の特定・発見に大いに役立つ情報であるからです。
また、すぐに警察へ110番通報し、事故の詳細と加害者が走り去ったことを報告しましょう。報告を受けた警察が少しでも早く捜査に取りかかることで、加害者を発見する可能性が高まります。そして、交通事故の目撃者がいる場合には、その目撃者の証言が加害者特定の重要な手掛かりとなります。そのため、目撃者の連絡先を聞いておき、証言を依頼しておくことも重要です。
-
交通事故によって負傷しました。この後どのような流れで進むのでしょうか。
まずは、医師に怪我の状態を見てもらい、必要な治療を受けてください。時間が経ってから症状が現れることもあるので、定期的に診察を受けましょう。
この後の流れは、治療の結果、症状が改善するか否かによって変わってきます。
(1)治療を受けたことで症状がなくなった場合
治療により症状がなくなった場合、事故日から症状がなくなった日までの間に発生した損害を相手方(の保険会社)に対して求めることができます。
ここでいう「損害」は、「治療費」だけでなく、治療のために休業せざるを得ず発生した「休業損害」や、事故による精神的苦痛を賠償する「慰謝料」なども含まれます。
損害額の算定は、被害者側で行う必要があります。症状がなくなった場合、相手方(の保険会社)と損害賠償について話し合いましょう(話し合いによる解決を「示談」といいます。)。示談が成立しない場合、訴訟を提起し、裁判で決着させることになります。(2)治療を受けても、症状が改善しない場合
治療を受けてもこれ以上症状が改善しない状態(この状態を「症状固定」といいます。)となった場合、それ以降に発生した治療費や休業損害は損害額に含まれません。その代わりに、症状固定前までの治療費や休業損害に加えて、「後遺障害逸失利益」や「後遺障害慰謝料」などが損害賠償の範囲に含まれます。
「後遺障害逸失利益」とは、事故によって後遺障害が残らなければ将来得られたはずの収入のことをいいます。そのため、後遺障害逸失利益の算定にあたっては、被害者の方の事故前の収入や、後遺障害の程度、今後どれくらい働くことができるかなどを考慮します。
詳しくは、こちらの回答をご参照ください。「後遺障害慰謝料」とは、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛を賠償するものをいいます。後遺障害慰謝料の金額は、ある程度類型化されていますが、弁護士が間に入ることで、高額な慰謝料の支払いを認める基準(一般に「弁護士基準(裁判基準)」と呼ばれています。)が認められます。詳しくは、こちらの回答をご参照ください。
相手方(の保険会社)に賠償額を支払ってもらうにあたっては、(1)と同様で、示談と訴訟による解決があります。損害額や示談・訴訟の選択について不安や疑問がありましたら、ぜひ一度専門家にご相談ください。
-
人身事故にあいました。今回の事故の件が最終的に解決するまで、どのくらいの時間がかかりますか?
人身事故の最終的解決するまでに要する期間は、事故状況や交渉の進捗具合により異なります。しかし、大まかな目安として、怪我の程度に応じて以下のような期間を要すると考えられます。
(1)後遺障害がない場合
症状が改善して治療が終了してから、示談交渉が始まります。示談交渉のために必要な書類を集めるのに1か月程度は要します。そして、示談交渉がスムーズに進んだとして場合には、1か月から1か月半程度で示談が成立することになります。一方で、示談交渉が難航している場合には3か月ほど示談成立に時間を要します。
また、示談成立後の「示談金の入金」には、1週間から1か月程度は要すると考えておきましょう。(2)後遺障害がある場合
この場合、示談交渉は後遺障害が認定された後に行われます。後遺障害の認定は、治療を受けてもこれ以上症状が改善しない状態(この状態を「症状固定」といいます。)となったと判断された後になります。そのため、症状固定後、後遺障害等級申請を行い、その認定を受けてから示談交渉が始まることになります。症状固定と診断から申請にあたって1か月~2か月ほどかかり、申請後に後遺障害等級認定を受けるのにも2か月ほど要します。
その後の手続きについては、概ね(1)と同じで、「後遺障害診断書」などの必要書類を準備し、示談交渉を行うことになるので、この準備に1か月ほどはかかると見ておいた方が良いでしょう。(3)死亡事故の場合
被害者が死亡した場合、一般に四十九日の法要が終わった後に、遺族の方々が中心となって、示談交渉のために必要な書類を1か月ほどかけて集めることになります。そこから示談交渉が始まるため、示談がスムーズに進んだとしても、示談成立が被害者死亡から半年程度要します。示談が難航している場合には1年以上の時間を要することもあります。
また、過失割合に争いがある場合、刑事裁判が始まった後に刑事記録を入手してから示談交渉が始まることもあります。この場合、さらに交渉開始時期が遅れることになるので、民事上の問題の解決には1年以上かかることも多いです。 -
運転中、対向車と接触し交通事故が発生しました。相手方に過失がある交通事故だと思うのですが、この場合でも、私の方から警察に報告した方が良いでしょうか。
はい。交通事故が発生した場合には、すぐに警察に報告しましょう。
その理由としては、以下の2点があげられます。(1)「交通事故証明書」を作成してもらうこと
警察に交通事故が発生したことを報告することで、警察は、事故状況やその発生原因を調査する現場検証が行います。この現場検証を基にして、「交通事故証明書」が作成されます。「交通事故証明書」は、交通事故が発生した事実を公的に証明する書類です。この書類は、様々な場面で必要となる重要な書類といえます。具体的には、①自賠責保険の被害者請求(又は加害者請求)を行う場合、②自己の加入する任意保険を利用する場合、③交通事故の症状を原因に休業する場合、④加害者に対して、損害の賠償を求める訴訟を提起する場合などには「交通事故証明書」が必要となります。このような重要な書類である「交通事故証明書」を作成してもらうには、まず事故のことを警察に伝えることが大切です。
(2)道路交通法上の義務であること
道路交通法72条は、交通事故が発生した場合に、人身・物損問わず、ドライバーが警察に事故が発生したことを報告する義務を課しています。具体的には、交通事故発生日時や場所、死傷者や損壊した物の有無、講じた措置などを報告しなければなりません。この報告を怠った場合には、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」が科せられます。道路交通法上の義務を守る観点からも警察への報告が必要です。
-
交通事故に遭い、怪我をしました。現時点では「物損事故」扱いとなっていますが、「人身事故」に切り替えてもらった方が良いでしょうか。
交通事故によってけがをした場合、基本的には警察に「人身事故」扱いにしてもらった方が良いケースが多いです。
人身事故扱いにしてもらった場合、警察は実況見分を行い、「実況見分調書」を作成します。この「実況見分調書」には、事故現場の見取り図や写真、事故状況などが記載されており、刑事裁判だけでなく、民事での争いにおいても証拠として利用することができます。そのため、「実況見分調書」は、当事者間で事故態様や過失割合などが問題となった場合などに、事故態様の立証することにとても役立ちます。一方で、物損事故扱いのままの場合、警察は実況見分を行わずに、「物件事故報告書」という簡易な書面が作成されるにとどまります。「物件事故報告書」は、警察官が測量などを行わないまま手書きで作成された「略図」などで構成されており、事故態様の立証するための証拠としては正直不十分であるといえます。物損事故扱いのままでも保険金の支払いを求めることはできますが、被害者側に有利な賠償金を得るためにも、人身事故への切り替えは積極的に行いましょう。
ただし、相手方(加害者)も怪我をしていて、双方に過失がある事故の場合に、人身事故に切り替えるように求めると、相手方も診断書を提出してくることが考えられます。そうなると、被害者も被疑者として扱われることになり、刑罰や、違反累積点数によっては行政処分(免許取り消し・停止など)を受ける恐れがでてきます。こうしたリスクがある場合については、人身事故切り替えのメリットと比較しつつ、人身事故への切り替えを要求するか否かを判断しましょう。
-
交通事故に遭い、怪我をしました。現時点では「物損事故」扱いとなっていますが、「人身事故」に切り替えてもらわなかった場合、不利になりますか。
交通事故により怪我をしたにもかかわらず、物損事故扱いとなっている場合、警察が「実況見分調書」を作成しないことから、被害者に不利益となることが考えられます。
人身事故の場合、警察は実況見分を行い、「実況見分調書」を作成します。この「実況見分調書」には、事故現場の見取り図や写真、事故状況などが記載されており、刑事裁判だけでなく、民事での争いにおいても証拠として利用することができます。そのため、「実況見分調書」は、当事者間で事故態様や過失割合などが問題となった場合などに、事故態様の立証することにとても役立ちます。
一方で、物損事故扱いのままの場合、警察は実況見分を行わずに、「物件事故報告書」という簡易な書面が作成されるにとどまります。「物件事故報告書」では警察官が測量などを行わないまま手書きで作成された「略図」が示されているなど、事故態様の立証するための証拠としては不十分であるといえます。
このように人身事故であれば「実況見分調書」が作成されるのに対し、物損事故であれば「物件事故報告書」が作成されるにとどまるという違いがあります。この違いから、以下のような違いが出てきます。
(1)①示談・判決内容への影響
「実況見分調書」は、警察が現地での実況見分を踏まえて作成した書類であるのに対し、「物件事故報告書」は、警察が自己地点と事後概要をメモとして記載した報告書であることから、証拠としての価値に大きな違いがあります。そのため、事故態様や過失割合が争われている場合、提示する証拠の信用性によって結論が変わってくることが十分考えられます。より信用性のある「実況見分調書」を提出することで、被害者に有利な内容で紛争を終わらせやすくなります。
(2)紛争解決までの時間への影響
「実況見分調書」と「物件事故報告書」には、作成過程の違いから信用性が異なります。そのため、事故状況自体について争われている場合、「物件事故報告書」しか提出されないと、事故状況がはっきりせず、紛争解決までに要する時間がより長くなる可能性が出てきます。被害者にとって、紛争解決までに時間がかかることは望ましいものとはいえません。そういったことを踏まえても、「実況見分調書」を出すことで、事故状況自体の争いを避けることが望ましいといえるでしょう。
ただし、常に人身事故扱いへと切り替えてもらった方がいいわけではなく、デメリットがある場合もあります。人身事故への切り替えのデメリットについては、こちらの回答をご参照ください。
-
交通事故に遭い、怪我をしました。現時点で「物損事故」となっており、「人身事故」に切り替えたいのですが、加害者が切り替えはしないでほしいと言ってきます。加害者が「物損事故」で留めようとするのは何故ですか。
「人身事故」の加害者となった場合、罰金や懲役などの刑事処分や、免許取消し・停止などの行政処分を受けるおそれがあります。一方で、「物損事故」の加害となった場合には、基本的に刑事処分や行政処分を受けることはありません。そのため、交通事故の加害者としては、物損事故扱いにしてもらった方が有利であるため、物損事故扱いにしようとします。
-
交通事故に遭い、怪我をしました。現時点で「物損事故」となっていることから、「人身事故」に切り替えたいと思い、警察に相談しました。しかし、警察は交通事故から時間が経っていることを理由に切り替えを拒んでいます。この場合、人身事故への切り替えはできないでしょうか。
法律上、人身事故への切り替えに時間制限はありません。しかし、警察は、人身事故への切り替えを受理するにあたって、なぜ直ちに人身事故として届け出なかったのかを当事者に確認することがあります。時間が経過すればするほど、「直ちに人身事故として届けなかった理由」を説明することは難しくなり、警察が切り替えに応じてくれなくなる可能性が高まります。
人身事故扱いにしてもらった方が良いか否かは、ケースバイケースです詳しくは、こちらの回答をご参照ください。それでも、人身事故扱いにしてもらった方が良いと考える場合には、客観的な証拠を示しながら、事故状況や怪我の深刻さについて説明しましょう。簡単には人身事故扱いへの切り替えが認められないことが想定されますが、粘り強く説明をして切り替えを認めてもらえるようにしましょう。
なお、物損事故扱いのままでも、(賠償額などに影響する可能性は否定できませんが、)保険会社に対して賠償を求めること自体は可能です。この場合、自賠責保険については、相手方の協力を得られる場合には「人身事故証明書入手不能理由書」を作成し、これを自賠責保険に提出することで、賠償請求が可能となります。
-
人身事故へ切り替えた方が、後に損害の賠償を求める際に有利になると聞きました。実際に「物損事故」から「人身事故」へ切り替えるにはどのようにしたらよいでしょうか。
物件事故扱いとされている交通事故であっても、人が負傷している場合には、人身事故に切り替えることができます。具体的には、診断書を病院で作成してもらい、その診療書を警察に提出することが必要となります。その際、診断書には、事故日と初診日、加療を要する期間が明記されている必要があります。
また、診断書を警察に提出する際、事故状況を把握できる資料(事故車両それ自体や損傷箇所が視認できるカラーの写真など)や、免許証、車検証などを持参するように求められることがあります。指示があった場合にはそれに従いましょう。
なお、診断書作成には費用がかかります。しかし、その費用は最終的に加害者側に請求することが可能ですので、その領収書は保管しておきましょう。 -
お互いに過失がある交通事故にあいました。この事故でケガをしたのは私だけで、相手の方はケガをしていません。この場合、人身事故として事故届をすると、私が行政罰や刑事罰を受けることがありますか?
互いに過失のある交通事故が発生した場合に、人身事故として届け出たときには、過失の認められるあなたは、行政罰として、運転免許についての行政処分を受ける可能性があります。あなたの運転にも過失があることで、違反点数付く可能性があるからです。あなたに既に違反累積点数がある場合には、今回の人身事故の違反点数が加算されることで、免許停止や取消しの処分がなされることがあります。逆に、物損事故であれば、通常違反点数が加算されることはありません。そこで、人身事故としての届け出を行う前に、ご自身の違反累積点数をご確認ください。
一方で、このケースで、あなたが刑事罰を受ける可能性は低いと思います。あなたの運転には過失があったかもしれませんが、相手方を負傷させていないため、過失運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)は成立しないと考えられます。また、相手方の自動車などを損壊させていた場合であっても、あなたのその行為が故意でない限り、器物損壊罪(刑法261条)は成立しません。
もっとも、交通事故が発生したにもかかわらず、このことを警察に報告(連絡)しない場合には、道路交通法上の違反となり、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」が科せられます。また、交通事故によって死傷者が出ているにもかかわらず、ひき逃げをした場合にも、道路交通法上の違反となり、「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
交通事故は突如起こってしまうものであり、事故直後は動揺されることが想定されます。しかし、慌てず、ひき逃げなどはすることはないようにし、安全を確保しつつ、救護や警察への連絡を行いましょう。
-
警察から事故について聞き取りを受けることになりました。警察の方からどういったことを聞かれるでしょうか。
警察から聞かれる事項としては、①事故の日時・場所、②事故状況、③怪我の有無・程度、④車両の状態(損傷の程度)、⑤証拠や目撃者の有無・情報、⑥加害者に対する処罰意思などが考えられます。
①~⑤の情報は、被疑者や事故態様、過失割合など、事故の全体像を把握するために確認されます。⑥の情報は、あなた(被害者)が加害者に対してどのような処罰処分(厳罰・適正・寛大な処罰処分)を望むかを把握するために確認されます。被害者であるあなたの処罰意思が処分内容に影響する可能性がありますので、事故態様や事故後の加害者の対応などを踏まえて判断しましょう。
上記の事項について警察に話す際には、正確な事実・記憶を基にして話すように心がけましょう。憶測や被害感情に起因する大げさな発言などはくれぐれも避けましょう。
警察は、あなたが話した内容を記録し、調書を作成します。そして、警察は、これを証拠とするために、あなたに調書の内容を読んでもらったうえで、署名押印を要求します。あなたの記憶内容と調書の内容が異なる場合には、訂正を申し出ましょう。もし、訂正ができない場合には、調書への署名は拒否すべきです。一度署名押印をしてしまうと、訂正をすることが著しく困難になるからです。
-
警察で事故の状況について話をすることになりました。どのような点に注意をすればいいですか。
事故状況について、記憶の通り話すようにしてください。分からないことは、無理に答えず、分からないと答える必要があります。警察から話の内容をまとめた調書を確認された時は、間違いがないか十分な確認が必要です。間違いがあれば訂正をお願いすることになります。
また、加害者の処分に対する希望を聞かれるかもしれません。厳しい処分・法律に基づいた適正な処分・寛大な処分等答えていただくことになります。 -
交通事故に遭い、治療をしている被害者です。加害者の保険会社から「同意書」なるものを提出するように求められました。これを提出した場合、被害者にとって不利になりませんか。
その同意書の内容によって、あなた(被害者)にとって有利なものか有利なものかが変わってきます。
まず、その同意書が、①加害者側の保険会社が一括対応するためのものである場合には、基本的にはこれに応じて同意書を提出して良いです。「一括対応」とは、加害者側の任意保険会社が被害者の治療費を直接病院に支払う対応をいいます。一括態様がなされていない場合、相手方が任意保険会社に加入していても、被害者の治療費は一旦被害者で立て替える必要があります。
しかし、一括対応がなされることで被害者が立て替える必要がなくなります。そのため、被害者が一括対応を受けることについて、基本的にデメリットはありません。
一方で、その同意書が、②医療照会・医療調査のための同意を要求しているものである場合には、被害者にとって注意が必要です。この場合、保険会社は一括対応の打ち切りを検討していると考えられるからです。とはいえ、同意書の提出に応じなければ、そのことを理由に一括対応を打ち切る可能性もあります。
そのため、上記②の同意書の提出を求められた場合には、同意書の提出には応じつつも、保険会社に「具体的な治療継続の必要性」を説明し、一括対応を継続することを求めることが大切になります。
-
交通事故被害者です。加害者が任意保険に加入していないことが発覚したのですが、自賠責保険から補償を受けることは可能でしょうか。
自動車を運転するためには、「自賠責保険」に加入することが法律上義務付けられています(強制加入の保険)。そのため、交通事故加害者が任意保険に加入していない場合でも、人身事故については、自賠責保険により、治療費や慰謝料、逸失利益(休業損害、後遺障害逸失利益など)の賠償金を支払ってもらえます。
しかし、自賠責保険で支払ってもらえる金額には限度があり、自賠責保険のみでは満足な賠償金を得られないことが多いです。具体的には、被害者が死亡した場合には3000万円、後遺障害を負った場合には4000万円、けがを負った場合には120万円が支払限度額となります。
したがって、相手方(加害者)が任意保険に加入していない場合に、自賠責保険では支払われない(補償されない)損害額は、加害者本人に支払ってもらうか、被害者ご自身で加入されている保険の人身傷害特約などで補う必要があります。
-
交通事故被害者です。加害者が「任意保険」だけでなく、「自賠責保険」にも加入していないことが発覚しました。加害者に財産がない場合、全く補償を受けられず、私は泣き寝入りするしかないのでしょうか。
相手方が任意保険だけでなく自賠責保険にも加入していない場合には、補償を受ける方法としては、①あなた(被害者)ご自身の加入する保険を利用する方法と、②政府保障事業を利用する方法があります。
①被害者の加入する保険を利用する方法
(1)搭乗者保険の利用 あなたの加入する自動車保険の中に「搭乗者保険」の特約は含まれていませんか。この保険は、運転者か同乗者かを問わず、契約車両に乗っている人が対象となります。死亡・後遺障害保険金や治療費などが補償内容となり、あらかじめ定められた定額の保険金が支払われることになります。
(2)人身傷害保険の利用 あなたの加入する自動車保険の中に「人身傷害補償保険」の特約は含まれていませんか。この保険は、交通事故の被害者(被保険者)に発生した損害を迅速に填補するものであり、自己の過失割合を考慮することなく、保険約款に記載された計算式に基づいて支払われます。人身傷害保険を利用しても保険料が変わらないことが多いので、いま一度ご自身が加入されている自動車保険に人身傷害保険特約が付されていないかご確認ください。
(3)無保険車傷害保険 あなたの加入する自動車保険の中に「無保険車傷害保険」の特約は含まれていませんか。この保険は、相手方が自賠責保険・任意保険いずれも加入しておらず、十分な補償が得られない場合に、交通事故の被害者(被保険者)に発生した損害を填補するものです。ひき逃げ等で加害者を特定できない場合にも利用することができます。また、搭乗保険や人身傷害保険と異なり、「加害者が負うべき賠償額」を保険金として支払いを求めることができます。
②政府保障事業を利用する方法
加害者が何らの保険に加入しておらず、あなた(被害者)ご自身の保険を利用することができない場合には、最終手段として、政府保障事業を利用することになります。
政府保障事業は、加害者が無保険である場合やひき逃げ等により加害者の特定ができない場合を対象としています。自賠責保険と同様に、対人賠償のてん補のみを対象とし、てん補を請求できる限度額も死亡・後遺障害・傷害でそれぞれ法律により決められています。
また、政府保障事業は、本来加害者が支払うべき賠償金を政府が立て替える性質のものであるため、その支払いまでには慎重な手続きを経る必要があり、相当な期間を要します。損害のてん補を求めてから、少なくとも6か月ほどは要することを前提に手続きの完了
-
相手が無保険で、自賠責保険にも入っていませんでした。自分の保険や政府保証事業からの支払いも受けることができません。この場合、加害者から支払いを受けることはできないのでしょうか?
相手方が無保険で、あなた(被害者)の保険や政府保障事業も利用できない場合、損害を賠償してもらえるかは、「相手方の資力」と「賠償金を支払う意思」の有無に依存することになります。
まずは、相手方(加害者)との間で、損害賠償に応じてくれないかを確認しましょう。相手方に資力があり、かつ、誠実に対応してくれる場合には、損害賠償額について交渉することも不可能ではありません。交渉においては、相場観を把握し、交渉経験豊富な弁護士に間に入ってもらうことで、適正な賠償額を獲得できる可能性があります。
一方で、「相手方の資力」又は「賠償金を支払う意思」がない場合には、損害賠償額を回収することが、かなり困難な状況にあると言わざるを得ません。この場合でも、弁護士に相談の上、損害賠償訴訟(裁判)を提起し、強制執行という手続きを経て、相手方の財産から賠償してもらう方法があります。しかし、相手方に賠償金を支払う資力がない場合には、相手方に賠償してもらうことがほとんど不可能でしょう。
また、資力があっても賠償金を支払う意思がない場合には、民事訴訟で勝訴判決を得るなどしたうえで、強制執行手続きにより、賠償金を支払ってもらう必要があります。そのため、あなた(被害者)が支払いを受けるまでに時間と労力を要することになります。
それでも泣き寝入りとなることは避けたいと考える方も多いかと思います。そういった場合には、他に採れる方法がないかを確認するためにも、一旦弁護士にご相談されることをお勧めいたします。