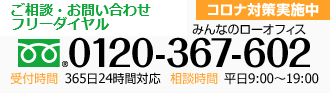治療についてのよくある質問
質問をクリックすると詳細が表示されます
-
交通事故に遭って怪我をしました。しかし、仕事が忙しかったので、まだ病院に行けていません。早く病院で診察を受ける方がいいでしょうか。
交通事故に遭われた場合、できる限り早く病院で診察を受けることを強くお勧めいたします。
この初診が遅れれば遅れるほど、事故と怪我の間の因果関係が疑われます。因果関係がないと判断されると、保険から治療費の支払が行われなかったり、後遺障害が認定されなくなったりする可能性があります。
どれほど時間が経過したら因果関係が疑われるかというのは、明確な基準はありませんが、事故日から1週間ないし2週間以内の初診がないと因果関係が否定される可能性が高まる傾向にあります。
ただし、これも明確な基準ではないため、これよりも早い段階で因果関係が否定されることもあり得ます。
そのため、交通事故に遭って身体に違和感がある場合には、できる限り早く病院で診察を受けましょう。 -
交通事故に遭いました。事故直後は痛みはなかったものの、数日経ってから身体に痛みが発生しました。今からでも病院で診察を受けた方がいいでしょうか。
事故発生から時間が経ってから、交通事故により負傷した怪我の痛みが出てくることもあります。
この場合、少しでも早く病院に行って診察を受けることをお勧めいたします。保険会社よる治療費の支払や、後遺症となった場合の後遺障害の認定を受けるには、医師の診断のもとで、病院やクリニックで治療を受けていることが重要となります。 事故日から初診が離れている場合、その痛みが交通事故によって発生したものではないとして、治療費の支払や後遺障害等級認定を受けられない可能性が高まります。事故日と初診日がどれほど離れていたら、これらのリスクが生じるかは明確ではありません。しかし、おおむね1週間ないし2週間ほど経過すると、治療費の支払などを受けられない可能性が高まります。
-
交通事故にあってケガをしました。事故にあった日から病院の初診日までの期間がどのくらい長くなると、事故とケガとの因果関係が否認されますか?
事故日から初診日までの期間が長くなると、交通事故によって、治療している怪我が発生したという因果関係が否定される可能性が高まります。因果関係が認められない場合、治療費などを加害者側に請求することができません。この期間について明確な基準はありません。
しかし、おおまかな目安として、事故日から1週間ないし2週間ほど経ってから初診を受けた場合、自賠責保険は、それを理由に因果関係を否定することが考えられます。自賠責保険がこのような判断をした場合には、対人賠償責任保険(相手方の任意保険)も通常は治療費を支払いません。
このように初診日は、今後の治療費や後遺障害等級認定などに影響を及ぼすおそれがあります。少しでも痛みを感じた場合には、すぐに受診をすることをお勧めいたします。
-
初診の診察の際に気を付けるべき点があれば教えてください。
まずは、医師に、痛みがある部位やその時点での症状を余すことなく伝えましょう。
当初は軽微な痛みと思われていた部位であっても、時間が経過することで痛みがひどくなることがあります。たとえ痛みが強いものであったとしても、事故日から時間が経って医師に伝えた場合、交通事故とその怪我との間の因果関係が争われる可能性が高まります。
因果関係が否定されると、治療費の支払を受けられなかったり、後遺障害等級認定を受けられなかったりします。そこで、初診時から症状をもれなく医師に伝えることが大切です。医師に伝えることで、その症状を訴えたことがカルテに残りますし、そのような記載があることで、事故と怪我の因果関係が争われた場合でも、初診日の時から痛みがあったとして因果関係が認められやすくなります。
-
交通事故に遭いました。事故状況からしても相手方の過失によって発生した事故だと思われるのですが、相手方は「あなた(質問者)の過失割合の方が高いはずだ」と言って、全く治療費を支払おうとしてくれません。治療費を補填してもらう方法はないですか。
交通事故の相手方(加害者)側が治療費の支払いを拒んでいる場合でも、以下の方法が使えるときには、治療費を補償してもらえることがあります。
(1)人身傷害補償特約
まずは、あなた(被害者)ご自身が加入している自動車保険に「人身傷害補償特約」が付されていないかご確認ください。この特約は、交通事故被害者が、速やかに保険金を受け取れるように設けられた保険ですので、過失割合にかかわらず、保険約款に記載された計算式に基づいた保険金額が支払われます。
(2)労災保険の適用
また、業務中または通勤中に交通事故に遭った場合には、労災保険を適用できる可能性があります。労災保険についても、労働者を保護するために設けられた保険制度であることから、過失割合にかかわらず、保険金が支払われます。具体的には、業務中の事故による怪我の治療費などとして「療養補償給付」や、通勤中の事故による怪我の治療費などとして「療養給付」が支払われることが考えられます。
(3)人身傷害補償特約や労災保険が使えない場合
人身傷害補償特約や労災保険が利用できない場合には、あなた(被害者)ご自身で健康保険を利用しつつ、治療費を立て替えていただくことになります。相手方が任意保険に加入している場合には、その保険会社に一括対応を求めることが考えられます(詳しくは、※【Q26】をご参照ください。)。任意保険会社が治療費の支払に応じない場合には、相手方の自賠責保険会社に請求することになります。
-
交通事故に遭って現在通院しています。病院へ治療費を支払う必要があると思うのですが、どのように支払ったらよいでしょうか。
加害者が任意保険に加入している場合、通常は、その保険会社が直接病院へ治療費を支払う対応が採られます(保険会社のこのような対応を「一括対応」といいます)。一括対応がなされた場合には、あなた(被害者)が治療費などを立て替える必要はありません。
しかし、一括対応は、あくまで相手方保険会社が任意に行っているサービスですので、保険会社が「事故と怪我の間の因果関係」や「過失割合」に納得いっていない場合には、一括対応を行わないこともあります。その場合には、あなたご自身で一旦治療費を立て替えていただくことになります。
その後は、自賠責保険へ被害者請求を行って自賠責保険金を受け取るか、示談や訴訟を通じて相手方の任意保険会社に支払って、治療費に充てることになります。
なお、あなたご自身が加入している自動車保険に「人身傷害補償特約」が含まれている場合には、相手方が治療費を支払ってくれないとしても、治療費を速やかに支払ってもらうことが可能です。
-
交通事故の治療費を加害者の任意保険会社が支払うことを「任意一括対応」というと聞きました。任意一括対応について教えてください。
「(任意)一括対応」とは、交通事故加害者側の任意保険会社が、被害者の治療費を直接病院に支払う対応のことをいいます。
被害者としては、治療費を立て替えたうえで、加害者(側の保険会社含む)に請求する手間を省くことができます。
また、一括対応を行った保険会社は、自賠責保険に対して求償を行うので、被害者としては自賠責保険に対する請求手続を行う必要もありません。保険会社に一括対応を行ってもらうには、被害者から加害者の任意保険会社に対して、事故の発生と一括対応を求めることを連絡する必要があります。
しかし、一括対応は、あくまで保険会社が被害者のために行うサービスの一環です。そのため、保険会社が「事故と怪我の間の因果関係」や「過失割合」について納得いっていない場合には、一括対応を行わないことや途中で一括対応を打ち切ることもあります。
この場合には、示談が成立するなど賠償額が決定するまで任意保険会社が治療費を支払ってくれる可能性は低いと考えられます。そのため、被害者自身が健康保険などを利用しつつ、治療費を一旦立て替え、加害者の自賠責保険会社に直接請求することが考えられます(「被害者請求」と呼ばれています)。
-
交通事故に遭ったのですが、事故当時痛みがなかった部位について後から痛みが出てきました。このような場合でも、加害者(の保険会社)に治療費を支払ってもらうことはできるのでしょうか。
事故直後には痛みがなかった部位に、後から痛みが発生した場合であっても、治療費を相手方(保険会社)に支払ってもらうこと自体は可能です。
しかし、事故日と初診日の間の期間が長くなれば長くなるほど、相手方は、事故と怪我の間の因果関係がないとして、治療費の支払いを拒むことが考えられます。医学的には、外傷による症状は、受傷の瞬間に最も強くなり、後は時間の経過とともに症状は軽減していき、悪化することはないと考えられているからです。
事故日と初診日にどれほどの期間が空くと、因果関係が否認されるという明確な基準はありませんが、おおむね1週間ないし2週間ほどが目安になると考えられます。
そのため、交通事故後に痛みを感じた場合には、それがわずかな痛みであったとしても、速やかに受診されることをお勧めいたします。その際は、後に保険会社と治療費について争いとなるリスクを減らすためにも、事前に連絡を入れておく方が良いでしょう。
-
交通事故に遭って、怪我の治療のため整形外科に行きました。その際、健康保険を利用したいと思ったのですが、病院から「交通事故の場合は健康保険を利用できない」と言われました。交通事故の場合、健康保険は利用できないのでしょうか。
大前提として、交通事故の場合であっても、健康保険を利用することは制度上可能です。また、厚生省(現・厚生労働省)も昭和43年に、「いうまでもなく、自動車による保険事故も一般の保険事故と変わりなく、(健康)保険給付の対象となるものである」という通達を出しており、交通事故の場合であっても健康保険を利用することは認められています。その場合には、加害者による記載も必要な「第三者行為による傷病届」の提出が求められます。
しかし、病院によっては、①そもそも「交通事故では健康保険を使えない」と勘違いしている場合や、②「健康保険での治療を認めない」とする場合もあります。①の場合には、弁護士から「交通事故でも健康保険を利用できる」と説明することで、健康保険を利用できるケースがあります。
また、②の場合には、弁護士が加害者又は被害者自身の保険では治療費を支払えない事情を説明して、病院と交渉することで健康保険を利用できる場合があります。
病院から健康保険の利用を拒まれ、交通事故の治療をどうすればよいのか不安に思われている方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
-
交通事故に遭って、治療のために病院に通っています。保険会社から、「治療にあたって、健康保険を利用してほしい」と言われました。保険会社の意図は何でしょうか。また、健康保険を利用すべきでしょうか。
保険会社が「健康保険を使ってほしい」と勧めるのは、治療費の総額を抑える点にあると思われます。あなた(交通事故の被害者)が健康保険を利用して治療を受けるべきか否かは、健康保険を利用のメリットとデメリットを考慮する必要があります(詳しくは、※【Q30】をご参照ください。) 。
少なくとも、①被害者にも過失がある場合(過失割合が問題となる事案)や、②加害者が無保険かつ資力が乏しく、十分な補償を得られない可能性がある場合、③加害者側が治療費の支払いを拒んでおり、被害者が立て替える治療費を軽減したい場合などには、健康保険を利用するメリットの方が大きいと考えられ、健康保険を利用する方が望ましいでしょう。
-
交通事故に遭って、治療のために病院に通っています。交通事故による傷病につき、健康保険を利用することのメリットやデメリットなどはありますか。
交通事故被害者の方が、治療のために健康保険を利用することはあります。もっとも、健康保険の利用には、メリットもデメリットもあるので、これらを踏まえて健康保険を利用するか否かを決定する必要があります。なお、健康保険を利用せずに診療を受けることを「自由診療」といいます。
(1)健康保険利用のメリット(2つ)
①過失割合が問題となる場合、健康保険を使うことにより、相手方に請求できる金額が高くなること。
被害者にも過失がある場合、過失割合に応じて、被害者も治療費を負担することになりますが、自由診療と健康保険利用を比較すると、自由診療の方が、治療費が高くなるからです。
②相手方(加害者)が無保険である場合に、リスクを軽減できること。
相手方が無保険であって、賠償金を支払う資力もない場合、被害者が治療費などを負担せざるを得ない最悪のケースも想定されます。
このような事態に陥る可能性がある場合には、自由診療よりも治療費を抑えることができる健康保険を利用しておいた方が良いでしょう。(2)健康保険利用のデメリット(2つ)
①健康保険ではできない治療があること。
健康保険では、行うことができる治療が限定されています。健康保険の対象外となる治療については、自由診療ということになり、治療費が高額になる可能性があります。
②「第三者行為による傷病届」の提出など、手続きが必要であること。
交通事故の被害者のように、第三者の行為によって負傷し、それを健康保険で治療する場合、「第三者行為による傷病届」の提出が必要となります。これに伴って、加害者の署名の必要な「誓約書」も提出が要求されることがあります。もっとも、加害者の協力を得られない場合であっても、健康保険を利用することは可能であるため、大きなデメリットとはならないでしょう。
-
通勤途中に交通事故に遭い負傷しました。この場合、病院で健康保険を利用することはできますか。
通勤途中に交通事故に遭った場合、「通勤災害」として労災保険を利用することができます(労働者災害補償保険法7条1項3号、21条以下)。そして、労災保険が利用できる場合には、健康保険は利用できないと法律で定められています(健康保険法55条1項)。労災保険が業務中や通勤中の怪我などを補償とする制度であるのに対し、健康保険は主にそれ以外の場合の怪我などを補償する制度であり、重複しないように設定されているからです。
そのため、まずは労災保険を利用できるかを確認し、利用できる場合には労災保険を利用しましょう。労災保険を利用できない場合であれば、健康保険を利用することができます。
-
仕事中に交通事故に遭い負傷しました。この場合、病院で健康保険を利用することはできますか。
お仕事中に交通事故に遭い、負傷した場合、「業務災害」として労災保険を利用することができます(労働者災害補償保険法7条1項1号、12条の8以下)。そして、労災保険が利用できる場合には、健康保険は利用できないと法律で定められています(健康保険法55条1項)。労災保険が業務中や通勤中の怪我などを補償とする制度であるのに対し、健康保険は主にそれ以外の場合の怪我などを補償する制度であり、重複しないように設定されているからです。
そのため、まずは労災保険を利用できるかを確認し、利用できる場合には労災保険を利用しましょう。労災保険を利用できない場合であれば、健康保険を利用することができます。
-
交通事故に遭い、治療のため通院していたのですが、治療の効果も出なくなったので、主治医に「後遺障害診断書」を作成してほしいと依頼しました。ところが、主治医からは「健康保険を利用していたため後遺障害診断書は作成できない」と言われました。健康保険を利用した場合、後遺障害診断書を作成してもらえないのでしょうか。
医師の中には、自賠責保険でなく健康保険を理由したことを理由として、「後遺障害診断書」の作成を拒否する方が実際にいらっしゃいます。
しかし、後遺障害等級の認定にあたっては、医者の見解や自覚症状の記載された「後遺障害診断書」の存在が特に重要になります。そのため、後遺障害診断書の作成を断られた場合であっても、粘り強く後遺障害診断書の作成をお願いする必要があるでしょう。場合によっては、弁護士に相談し、弁護士に対応してもらうことも一つの手段です。ただし、弁護士が対応しても、頑なに後遺障害診断書の作成に応じない医師も稀にいらっしゃいます。そういった場合には、その地域の意思の傾向を把握している法律事務所に依頼することで、そのような事態を避けやすくなります。ぜひ一度弁護士にご相談ください。
-
交通事故に遭い負傷しました。そこで、整骨院に行こうとしたのですが、保険会社から「医師の指示・同意なく整骨院に行った場合は、その施術費を支払わない」と言われました。医師の指示や同意なく整骨院には行かない方がいいのでしょうか。
交通事故の治療として整骨院に行く場合、医師の指示・許可を得るべきです。裁判において「整骨院の施術費」が争いになった場合、「その施術についての医師の指示や許可があったか否か」が重視されることになるからです。
医師の指示・許可を得ることで、整骨院での施術が医学的に有効かつ相当であることを証明しやすくなり、施術費も治療費の一部として賠償を求めやすくなります。逆に医師の指示・許可なく整骨院で施術を受けた場合、その施術が医学的に有効かつ相当とは認められず、保険会社から治療費として支払いを断られる可能性が高まります。
また、後遺障害が残った場合に、後遺障害認定を得るには、治療は医師が行っていたことが前提となります。そのため、適切な後遺障害認定を得るためにも、整形外科にも定期的に通院し、そこで医師の指示・許可を受けた範囲内で整骨院に通うことが大切です。
-
整形外科での治療にあまり治療効果を感じていません。整骨院で治療をすることはできますか?
整骨院に通って施術を受けること自体はもちろん可能です。
しかし、整形外科の医師の指示や許可がないまま、施術を受けた場合、その施術費を保険会社に支払ってもらえなくなる恐れがあります。「整骨院の施術費」が裁判において争われる場合、「医師の指示・許可を得た施術か否か」が重視されるからです。医師の指示・許可のない施術は、医学的に有効かつ相当と認められず、保険会社が治療費として支払うことを拒むことがあります。
したがって、整骨院に通い始める前に、医師から整骨院に通うことについての指示・許可を得た方が良いです。 なお、医師が整骨院への通院を許可しない場合については、※【Q43】をご参照ください。
-
整骨院で治療を始めたので、整形外科には、もう通院しなくても良いですか?
整骨院への通院はやめることなく、整形外科と整骨院を併用することを強くお勧めします。
相手方保険会社に対して、「整骨院での施術費」を治療費として支払いを求める場合、その施術が医学的に有効かつ相当であると認められる必要があります。そのためには、医師に整骨院で施術を受けることの指示又は同意を得る必要があるとともに、定期的に整形外科の医師に経過状況を診てもらい、その有効性を確認してもらう必要があるからです。実際、「整骨院の施術費」が裁判において争いになった場合、「医師の指示や許可があったかどうか」が重視されますので、医師の判断がないまま整骨院のみに通うことは避けましょう。
-
整骨院での治療と整形外科での治療は、どのような違いがありますか?
「整形外科での治療」と「整骨院での施術」には以下のような違いがあります。交通事故に遭った場合には、特に(3)の違いが重要になります。
(1)診療・施術内容の違い
「整形外科」では、医師が診察・治療を行います。西洋医学に基づき行われ、怪我や病気の症状(病名)を特定し、その症状に対応した手術や治療、投薬などを行います。レントゲン撮影やMRI検査などを行うこともあります。
「整骨院」では、柔道整復師が施術(手技療法や物理療法)を行います。東洋医学に由来し、なぜそのような症状になったのかという原因を特定し、それぞれの患者に合った施術を行います。マッサージやストレッチなどもしてもらうことができ、すぐに効果を実感しやすい場合があります。(2)営業時間の違い
「整形外科」の傾向としては、土曜を営業していないところが多く、営業していても午前中のみなどの整形外科が多いです。夜間営業や日祝営業を行っている整形外科はほとんどありません。
「整骨院」の傾向としては、土曜も平日同様に営業しているところが多いです。また、夜間営業などを行っている場所も多く、仕事終わりなどでも通いやすいです。さらに、日祝も営業している店もあります。(3)交通事故の損害賠償での違い
「治療費・施術費が、交通事故の損害として賠償を求めることが認められるか否か」については大きな違いがあります。
「整形外科での治療費」は、交通事故によって生じた損害(治療費)として、基本的に加害者に賠償を求めることができます。
「整骨院での施術費」は、加害者が支払いを拒んだ場合に、賠償を受けられない可能性があります。「整骨院の施術費」が裁判で争われた場合、その施術が医学的に有効かつ相当と認められる場合を除き、交通事故によってして生じた損害(治療費)と認められません。そのため、整骨院での施術費を相手方に賠償してもらうには、事前に医師から整骨院に通うことの指示・許可を得た上で、医学的に有効かつ相当と認められる施術であることが重要となります。 -
整骨院で治療をする際の注意点を教えてください。
整骨院で施術を受ける際には、以下の点に注意しましょう。
(1)医師の指示・許可がない施術の場合、施術費を加害者側に負担してもらえなくなる可能性があること。
加害者側の任意保険会社が「整骨院の施術費」の支払を拒む場合、この施術費の賠償を保険会社に請求できなくなる可能性があります。保険会社が施術費を支払わないため、裁判で「整骨院の施術費」が争われる場合には、「その施術が医師の指示・許可を得て行われたものか否か」が重要になります。
医師の指示・許可を得た施術であれば、裁判所が、医学的に有効かつ相当として賠償を求めることが考えられるからです。したがって、整骨院で施術を受ける場合には、あらかじめ医師の指示・許可を得たうえで通院した方が施術費を支払ってもらいやすいといえます。整形外科(病院)と整骨院に並行して通院する場合でも、まずは整形外科で医師の指示・許可を得ておきましょう。
(2)整骨院への通院頻度に気を付けること。
交通事故で負傷し、整骨院に通う場合、その通院頻度が多くなりすぎないように気を付けましょう。任意保険会社が治療費の打ち切りを早めに行うことがあるからです。おおまかな目安ではありますが、週5回以上の整骨院への通院があると、治療費支払が打ち切られやすくなります。
-
鍼治療を受ける時の注意点を教えてください。
「はり・きゅう(鍼灸)」の施術には、血行を促進することで自然治癒力を高めたり、慢性的な痛みを軽減したりする効果があるといわれています。 もっとも、交通事故被害者の方が、鍼治療を受け、その施術費を相手方保険会社に請求しようと考えている場合には以下の注意が必要です。
(1)はり・きゅう施術には、医師の同意が必ず必要であること。
鍼灸院でのはり・きゅう施術にあたっては、医師の同意書が必須となります。はり・きゅう施術は、医師が医学的見地から治療手段がなく、施術が必要と判断した場合限って行うことができます。整骨院での「あん摩・マッサージ・指圧」療養については、医師の同意が必ずしも必要ではないので、はり・きゅうと大きな違いがあるといえます。
(2)必ずしも交通事故加害者側に施術費を支払ってもらえるわけではないこと。
交通事故によって負傷し、はり・きゅうの施術を受けた場合、その施術費を加害者側に請求することが考えられます。しかし、裁判において、「はり・きゅう施術費」の支払いを加害者側に求める場合、その施術が医学的に有効かつ相当と認められることが必要と考えられています。 もしはり・きゅう施術費について賠償を求めることができるか否か不安がありましたら、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
-
整骨院と接骨院に違いはありますか?
整骨院と接骨院は、名称が異なるのみで、施術内容や柔道整復師が行う点で違いはありません。
なお、交通事故により負った傷病を治すために整骨院(接骨院)に通う場合、事前に医師の指示・許可がないと、保険会社が施術費の支払いを拒むことがあります。あなた(被害者)個人の判断で、整骨院に通った場合、その施術費は自己負担となる可能性が高まります。そのため、整骨院に通う場合、可能な限り医師の指示や同意を得てから通う方が望ましいといえます。 -
交通事故のケガの治療として整体で治療をすることはできますか?
「整体院」では、身体の不調(肩こりや腰痛など)を良くするために、骨盤や背骨を正しい位置に整える施術などを行います。ただし、整体院で施術を受ける際には、以下の点に注意する必要があります。
なお、名称が類似した「整骨院(接骨院)」との混同に注意する必要があります。(1)健康保険・労災保険を利用できないこと。
「整体院」では、健康保険や労災保険などを利用することができません。一方で「整骨院(接骨院)」では、健康保険や労災保険を利用できますので、混同しないようにする必要があります。
(2)交通事故加害者側に施術費を支払ってもらうことが困難で、自費で施術を受けることになること。
交通事故で怪我をして、その痛みを和らげるために「整体院」で施術を受けることは考えられます。しかし、交通事故加害者(の保険会社)に、その施術費を支払うことを拒絶された場合には、自費で施術を受けざるを負えないと考えられます。 裁判においては、「整骨院(接骨院)」での施術費は、その施術が医学的に有効かつ相当と認められる場合には、加害者側に支払義務があると考えられています。
このような「整体院」での施術の特徴を踏まえると、加害者側に施術費を支払ってもらえると思って、安易に整体院に通うことは、リスクが高いといえます。
-
交通事故の治療を整骨院・鍼灸院でする場合、健康保険を使用することはできますか?
交通事故の施術を整骨院や鍼灸院で行う場合、健康保険を利用することができます。
もっとも、医師から整骨院や鍼灸院で施術を受けることについて指示・許可を得ていない場合、その治療費の自己負担分(基本的に3割)を相手方保険会社に請求することができなくなる恐れがあります。そのため、自己負担なく整骨院や鍼灸院で施術を受けるには、事前に医師の指示・許可を得て、その施術が医学的に有効かつ相当なものであると認めてもらうことが大切です。なお、「整体院」での施術には、健康保険を利用できません。注意が必要です。
-
通院している整形外科の医師が整骨院での施術は認めない医師です。しかし、整骨院での施術も受けたいです。どうすれば良いですか?
整骨院での施術を認めないお医者さんも実際にいらっしゃいます。
しかし、医師の指示・許可なく整骨院の施術を受けた場合、相手方保険会社にその施術費の支払いを求めるが難しくなる恐れがあります。そのため、自己負担なく整骨院で治療を受けたい場合には、医師との相談の中で、整骨院での治療の必要性を説明し、指示や許可を得た方がよいでしょう。医師から整骨院への通院の許可が出ない場合には、整骨院への通院を許可してくれる整骨院に転院することも考えられます。ただし、事故から2~3か月ほど時間が経過すると、保険会社が転院を認めないことも考えられます。そこで、どうしても整骨院で施術を受けたい場合には、事故から1~2か月くらいまでに転院の上、整骨院で施術を受けられるようにしましょう。
なお、整骨院では健康保険を利用することができるため、一部の自己負担(3割)で整骨院に通院することも考えられます。もっとも、弁護士に相談し、医師や保険会社との交渉を行ってもらうことで、自己負担なく整骨院で治療を受けられる可能性があります。
-
通院している整骨院の担当の柔整師さんから、「毎日通院するように」と言われていて、そのとおり、毎日通院しています。仕事もあり、毎日通院するのは大変なのですが、言われたとおり、毎日通院した方が良いでしょうか?
整骨院に通うことで、マッサージなどの施術を受けることができ、怪我の痛みなども和らげることができるかと思います。
しかし、通院頻度が多すぎると、相手方任意保険会社から、早めに治療費が打ち切られる可能性があります。具体的には「週5日以上、整骨院に通う場合」には、早期打ち切りの可能性が高まりますので、通院頻度には気を付けましょう。 -
交通事故に遭い負傷し、現在通院しています。しかし、通院中の病院の対応がよくなく、他の病院に転院したいと考えています。転院することは可能でしょうか。また、保険会社との関係で何か問題は発生しないでしょうか。
通院先を変更すること(転院すること)自体は可能ですが、以下の点に注意する必要があります。
(1)①転院をきっかけに治療費支払いを打ち切られる(終了する)可能性があること。
軽傷の事案で、事故から2~3か月経過後に転院をしようとする場合、治療費支払の打ち切りを検討していた相手方保険会社が、これをきっかけに治療費支払いを打ち切る恐れがあります。実際に治療費の支払を打ち切られた場合、基本的には被害者の方で治療費を立て替えていくことになります(後から相手方の自賠責保険や任意保険会社に請求することになります。)。
(2)②慰謝料の減額や、後遺障害等級認定への悪影響のリスクがあること。
転院を繰り返していると、そもそも治療の必要性が欠くのではないかと判断されたり、症状の経過観察が十分に行われていないと判断されたりする恐れがあります。こうなると、相手方保険会社からの治療費の支払がなされても、慰謝料が減額される恐れや、満足のいく後遺障害等級認定がなされない恐れがあります。
したがって、転院にあたっては、今一度なぜ転院する必要があるのかを考えましょう。どうしても必要と考えるのであれば、医師に相談の上、相手方保険会社とも連絡を取っておきましょう。
-
治療中に転院する場合の手順を教えてください。
転院する場合、以下の順序で、現在の通院先・転院先・相手方任意保険会社との連絡を取ることをお勧めいたします。
(1)①現在の担当医に転院したい旨を伝えること。
この際に、転院の了承を得るとともに、紹介状を記載してもらえると転院がスムーズになります。
(2)②転院先の病院を決定すること。
もちろん、転院前の病院に通院している時点から転院先を探していても構いませんが、治療などへの影響が出ないようになるべく早く転院を実現しましょう。
(3)③相手方任意保険会社に「転院すること」・「一括対応を継続して欲しいこと」を伝えること。
転院先が決まった場合、転院先への通院を始める前に、相手方任意保険会社に連絡をしましょう。具体的には、「転院先の情報」と「一括対応を継続して欲しいこと」は伝えましょう。一括対応をしてもらえる場合、被害者の方が治療費を立て替える必要がありませんが、このサービスを受けるには、上記の情報を提供することが必要です。
ただし、転院をすることにはリスクもあります。詳しくは、※【Q45】をご参照ください。
-
保険会社が転院を認めなかった場合は、転院を諦めて元の整形外科に通い続けるしかありませんか?
まずは、①転院の理由(必要性)を再度保険会社に説明し、了承を得られるようにしてみましょう。この理由が合理的なものでなければ、保険会社を翻意させることは難しいので、今一度転院をする必要性を考えてみましょう(例 通院先の病院が遠いこと、治療の効果が出ていないこと)。
それでも保険会社が翻意しない場合には、②別の医師にセカンドオピニオンを求めたうえで、その医師から転院の必要性を説明してもらうこと、③弁護士に相談の上、保険会社との交渉をしてもらうことが考えられます。
-
転院する場合に、元の整形外科からの紹介状は、必ず必要ですか?
紹介状がなくとも転院することは不可能ではありませんが、以下の点から、紹介状を作成してもらった方がよいと考えられます。
まず、①紹介状がある場合、保険会社が治療費の支払を継続して認めることが多いです。紹介状があることで、医師が認めた転院の合理的理由があることが示されるからです。
また、②紹介状があることで、病院間でのスムーズな治療の引継ぎが可能です。紹介状には、治療の履歴や検査結果も記載されていることから、転院先の病院でも無駄なく治療を引き継ぐことができるからです。
紹介状がなければ、保険会社が治療費を支払ってくれないリスクや転院先の病院とこれまでの治療の履歴等について逐一確認しながら通院することになるので、あなた(被害者)の負担は大きくなります。そういった観点からも、可能な限り紹介状を取得の上、転院の手続きを行いましょう。
-
転院した場合のデメリットを教えてください。
転院した場合のデメリットとして、①治療に関する負担が生じることと、②金銭的な負担が生じることに分けることができます。
まず、①転院前と転院後の病院間で、これまでの治療履歴や検査結果などが十分に共有されない場合、必要な治療を受けられなかったり、重複する検査を受けたりする可能性があります。そのため、あなた(被害者)にとって、治療が負担となる恐れがあります。
また、②保険会社が転院を認めない場合、保険料の支払が行われなくなることがあります。実際に支払われなくなった場合、治療費は自己負担となるため注意が必要です。もっとも、転院に合理的な理由がある場合には、保険会社が転院を認めることもあります。医師に転院の相談をしたうえで、紹介状を書いてもらうなどして、保険会社を納得させることが大切です。
-
ケガの痛みで運転がままならないので、タクシーで通院したいと思っています。タクシー代を請求できますか?
タクシー代が請求できるのは例外であり、基本的には、公共交通機関の運賃か自家用車のガソリン代の限度で支払われます。足の骨折といったタクシーを利用しなければならない事情がある場合には、タクシー代が認められやすくなります。
タクシー利用を予定している場合には、あらかじめ保険会社にタクシーを利用したいことを伝え、協議しておきましょう。
-
自家用車で通院をした場合、交通費を請求できますか?
交通事故により負傷し、自家用車で通院することになった場合、そのガソリン代を通院交通費として、加害者(の保険会社)に請求することができます。
そして、ガソリン代は、「1キロにつき15円」として、それに「家と病院の往復にかかる距離」をかけ、算出することが多いです。もっとも、高速道路を利用した場合に、「高速道路料金」も請求できるか否かはケースバイケースです。下道では病院に通院するまで長時間運転となるなど、高速道路を利用せざるを得なかった理由がある場合には、その請求も認められやすくなるといえるでしょう。
なお、病院の駐車場が有料である場合には、その駐車場代も加害者側に請求することが可能ですので、その領収書は保管しておきましょう。 -
家族の看護・見舞いのために交通費を請求することはできますか?
まず、①交通事故被害者の家族が「看護(付添い)のために要した交通費」については、看護・付添いの必要性が認められる場合であれば、被害者本人の損害として加害者側に請求できるケースが多いです。最高裁判例の中には、交通事故により瀕死の重傷を負った被害者の娘が、「海外(モスクワ)から付添いのために緊急帰国した際の交通費」も損害賠償の対象となると判断したものがあります。このように看護・付添いのための交通費については、その金額が高額となる場合でも認められることが多いです。
また、②交通事故被害者の家族が「お見舞いのために要した交通費」については、ケースバイケースではあるものの、認められることはあります。そこでは、お見舞いの必要性・相当性が認められることが重要ですが、被害者の負った傷病の状況・緊急性、被害者と家族の関係性、被害者の年齢、お見舞いの頻度、家族としての心境などを踏まえて判断されます。
-
医師から入院するかどうかは患者の意思に任せると言われました。入院しても大丈夫ですか。
基本的には問題ありません。ただ、後で保険会社が入院の必要性がなかったとして入院費の支払を拒むかもしれません。そのため事前に保険会社に連絡をとり、入院する旨を伝えておくべきでしょう。
-
入院したいのですが、個室は使用できますか。
個室使用料は怪我の程度や治療内容などに応じて医師が必要と認めた場合のみ認められます。
そのため、まずは医師に相談して、個室の使用が必要であるとの診断書を作成してもらうといいでしょう。 -
交通事故に遭い、治療のため入院しています。この間家族が付き添ってくれているのですが、家族の交通費や休業損害については、相手方に請求することはできるのでしょうか。
傷害の内容や程度等により、必要かつ相当と判断された場合には入院付添費(原則日額6500円)や交通費が認められます。
医師の指示があったり、幼い子の場合には、認められやすくなります。
なお、休業の補償が認められなくても、お見舞いのための交通費が認められることはあります。 -
交通事故で重傷のケガをして入院治療をすることになりました。保険会社から、健康保険を使うように言われているのですが、保険会社のいうとおりに健康保険を使った方が良いのでしょうか。
保険会社としては、自由診療よりも健康保険を利用した治療の方が治療費が安くなり、賠償額も小さくなることから、あなたに健康保険を利用するよう伝えていると考えられます。健康保険を利用することにはメリット・デメリット双方が考えられます。その指示に従うかは慎重に判断する必要があります。
まず、メリットとしては、①あなた(被害者)側にも過失がある場合、相手方に請求できる金額が大きくなる点です。健康保険から支払われる給付額が過失相殺前に損害額から控除されるため、医療点数単価が低い健康保険を利用していた方が、最終的に請求できる金額が高くなるからです。
また、②仮にその治療費が自己負担となった場合に、その負担額を3割に軽減することができる点です。もっとも、本件のように、保険会社が認めている怪我の治療費につき、自己負担を強いられることは考えられにくいです。そのため、自己負担となるリスクが高い場合以外は、この点を考慮する必要性は低いといえます。
一方で、健康保険を利用するデメリットとしては、①病院が交通事故治療について健康保険利用を認めない場合があることです。このような病院の場合、「自賠責診断報酬明細書」等の書類を作成してくれず、後遺障害申請の場面などで支障をきたすおそれがあります。後遺障害等級の認定の有無は賠償額に大きな差をもたらすので、大きなデメリットとなります。また、②仮に健康保険を利用できるとしても、「第三者行為による傷病届」の提出が要求されるため、手続き的な負担を強いられます。
以上から、あなた側に過失がなく、加害者側の保険会社も治療自体は認めている場合には、病院が健康保険の利用を認めているときを除き、そのまま自由診療を選択する方が無難といえるでしょう。ただし、後の損害額に大きな影響をもたらしうる判断にはなるため、医師だけでなく、弁護士に相談することもとても有効です。
-
交通事故でけがをして治療中ですが、加害者側の保険会社の担当者が「症状固定」という言葉をよく使ってきます。「症状固定」とはどういう意味でしょうか。
症状固定とは、医師によるけがの治療の結果、これ以上治療をしても症状の改善が見込めない状態をいい、その症状固定の状態になった日を症状固定日といいます。症状固定の時点で、けがを原因とする何らかの症状が残っている場合、その症状は「後遺障害」となります。
賠償実務においては、症状固定日までが治療期間であり、症状固定日後は治療終了後の後遺障害という扱いになります。そのため、症状固定日は、(1)損害算定のための時的区分となる (例えば、負傷により働くことができなかった損害は、症状固定日以前については休業損害として、症状固定日以後については原則として後遺障害による逸失利益として検討されることになります)、(2)いわゆる中間利息控除の起算点となる、(3)後遺障害による損害についての消滅時効期間の起算点となる、(4)症状固定後に支出した治療費は原則として損害として認められないことになるなど、損害賠償実務において、重要な意味を持っています。
なお、この症状固定の時期については、治療費の打ち切りにも関係することから、加害者の加入する保険会社と被害者側の間でよく争いとなります。
納得がいかないようであれば弁護士に相談されることをお勧めします。 -
身体がまだ痛いのですが、症状固定しなければならないのでしょうか。
受傷内容と症状経過、治療期間によります。
通常、頚椎捻挫等の神経症状の場合、適切な治療を半年程度受けても症状が後遺しているのであれば、症状固定をし、後遺障害の認定を受けるべきでしょう。 症状改善のために治療を受けたにもかかわらず、残っている症状がまさに、後遺障害だからです。
ただ、この残った症状が、自賠責保険の規定する後遺障害等級に該当するかどうかは、後遺障害認定を受けなければなりません。 -
交通事故遭い、治療中だったのですが、相手方保険会社から「治療費の支払の打ち切る」と伝えられました。保険会社が症状固定と判断した場合、もう保険会社に治療費を支払ってもらうことはできないのでしょうか。
「症状固定」は、治療をこれ以上継続しても症状の改善が見込めない状態のことを言います。
保険会社が治療費の支払を打ち切った場合、これまで行っていた一括対応(保険会社が治療費を直接病院へ支払うサービス)をやめる対応をとったことになりますが、必ずしもこの時点で症状固定に至っているとは限りません。一括対応をやめることは保険会社の判断にすぎず、医師が判断する症状固定時期とは必ずしも一致しません。
そのため、①症状固定に至っていなかった場合には、保険会社に対し、実際の症状固定時までの治療費の支払いを求めることができます。もっとも、この場合であっても、被害者の方で一旦は治療費を立て替えなければなりません。
一方で、②一括対応取りやめの時期と症状固定時期が一致する場合があり、それ以降の治療費は被害者負担となります。
以上のことから、一括対応が取りやめられた時点で、医師の見解を聞き、自費での通院を継続すべきかを判断することが必要となります。 -
保険会から治療費の立替払いを打ち切ると連絡がありました。弁護士が交渉をして、治療費の立替払いを延長することができますか?
個別の事案の状況にもよりますが、弁護士が保険会社との連絡・交渉を行うことで、治療費の立替払いが延長されることは十分考えられます。弁護士は、保険会社の打ち切り理由(たとえば、治療が必要以上に長期化しているなど)を聞いたうえで、被害者(依頼者)の症状と傷病名などを確認したり、医師との面会を行ったりします。これを踏まえて、妥当な治療プランを検討し、保険会社にも共有して、治療費の支払を継続してもらうように交渉を行います。保険会社との交渉の経験が豊富な弁護士は、保険会社を納得させる交渉のノウハウを有しているといえるでしょう。
-
保険会社が治療費の立替払いを一方的に打ち切ってきました。保険会社を訴えて、治療費を立替え払いをさせることはできませんか?
症状固定前の治療費については、加害者の保険会社に対して支払うことができます。
「症状固定」とは、治療をこれ以上継続しても、症状の改善が見込めない状態のことを言いますが、この状態にあるか否かは医師が判断します。
そのため、保険会社が治療費の立替払いを打ち切った場合であっても、必ずしも症状固定に至っているとは限りません。したがって、このような場合には、症状固定に至るまでの治療費は、後から保険会社に対して請求することができます。 -
交通事故でむちうちのケガをし、通院治療を続けています。病院や整骨院に通院してリハビリをした日は症状はやわらぐのですが、また次の日は症状がぶり返します。治療を受けた日は症状が緩和して、次の日には、また元に戻るということの繰り返しです。治療はいつまで続けるのが良いのでしょうか。治療のやめ時の判断をどうすれば良いのかわからないので教えてください。
加害者の保険会社に治療費の負担を求めることができるのは「症状固定時」(治療をこれ以上継続しても、症状の改善が見込めない状態)までであるため、漫然と治療を続けると、症状固定後も治療を続けてしまい、治療費が自己負担となるおそれがあります。むち打ちの治療期間としては、一つの目安として6か月とされていますが、事故態様や衝撃の強度、治療方法などによって前後することが考えられます。
そのため、現在の治療の効果に疑問がある場合には、医師に相談したうえで、より適切な治療がないかを確認しましょう。セカンドオピニオンとして別の医師に確認する方法もあります。
また、加害者の保険会社としては、治療をしても症状をぶり返す状況にある以上、治療費の立替払いを打ち切ってくる可能性があります。打ち切りを避けるには、治療の効果があることを説明し、納得してもらう必要があります。むち打ちの場合、保険会社としては遅くとも6か月を経過する頃には打ち切りの連絡をしてくることが考えられます。以上のことから、まずは「医師の見解を踏まえた治療」を継続することが大切です。また、保険会社からの打ち切りの連絡などがあり、その対応に苦慮した場合には、弁護士に相談し、保険会社との交渉を依頼することも一つの手段といえるでしょう。
-
症状固定の判断は誰がするのですか。
医学上の判断としては、医師がお客様の症状を見て、判断します。
ただ、一括対応に応じる期間の判断は、保険会社がしますので、治療期間の判断はまず保険会社が一方的に行ってくるという事実もあります。
その後、適切な治療期間はいつまでかを争う中で、最終的には裁判所が症状固定日を判断することになります。 -
症状固定と診断された後も病院に行ってもいいのですか。
行っていただいてかまいません。
症状固定後の治療費に関しては、原則として相手方から回収することはできませんが、後遺障害の残存を立証するためなどに必要となることもあるので、領収証はきちんと保管しておいてください。
-
交通事故に遭って治療を続けてきましたが、保険会社から症状固定と言われました。症状固定になるとどうなるのですか?
症状固定とは、治療を続けてもこれ以上症状の改善が見込めない状態のことを指します。
症状固定までは、保険会社から治療費・休業損害が支払われますが、症状固定になると、治療費・休業損害の支払いが止まります。
症状固定後は、慰謝料や、後遺障害が残る場合は逸失利益として、まとめて保険会社から支払を受けることになります。症状固定時点で症状が残り、後遺障害認定の可能性があるときは、主治医の先生の後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害の申請を行う必要があります。
保険会社との示談交渉は、後遺障害の判断が出た後に行います。 -
小学生の息子が、交通事故で大腿骨を骨折する重傷のケガをしました。手術も無事に成功し、経過も良好で、治療は終了となりました。ただ、成長の過程で、高校生くらいになってから再手術が必要であると主治医の先生から言われています。症状固定としてしまうと、将来、再手術が必要となった時の治療費は自己負担になるのでしょうか?
たしかに「症状固定後の治療費」については、原則として加害者の保険会社に請求することはできません。もっとも、これまでの裁判例を踏まえると、症状固定後の治療費(将来の手術費・治療費)についても、その支出が相当なものといえる場合には、加害者に対して請求することができるケースがあります。
小学生の息子さんが事故に遭われ、大腿骨を骨折する怪我を負ったことですが、一旦は治療が終了しておりますので、症状固定がなされた状況にあると思われます。もっとも、これから成長期を迎えるため再度の手術の必要性があると主治医に判断されていること、大腿骨という歩行のために不可欠な部位に重傷を負っていることなどを踏まえると、その手術費用の支出も相当なものに当たる可能性があるといえます。
「症状固定後の治療費」を加害者の保険会社に請求することは、容易いことではありませんが、賠償金額に大きな差が生じます。ぜひ弁護士にご相談ください。